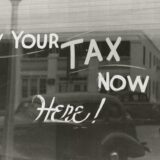Photo by Scott Graham on Unsplash
この記事を読んでいる人は、固定資産税評価額は不動産にかかる税金を算出するときの基本の情報になっていることを理解されている方だと思います。
固定資産税評価額の計算はいろんな用語が出てきて、「結局、何を見ればわかるんだ??」と思ったことがある人は少なくないと思います。
そこで、この記事ではご自分の購入しようとしている不動産の固定資産評価額をご自分で求められるようにまとめましたので、お役に立てれば幸いです。
固定資産税評価額を算出しようとすると、下記の用語が所々に出てきます。
たくさん出てき過ぎて、私はいチンプンカンプン、処理しきれなくなりました。
そこで下記の項目について、それぞれの背景や役割、それらの関係性をこの記事でまとめてみました。
税金の計算に用いられる価格の種類
- 固定資産税評価額
- 路線価
- 公示地価
- 公示価格
- 課税標準
- 基準値標準価格
- 相続税評価額
などなど、色々な名前がありますね。
それでは個別にみていきましょう!
固定資産税評価額
- 決定する機関 市町村
- 公示価格を100%とすると、その70%の価格になる
- 基準日 1月1日 3年に1度変更される
- 公表日 3月または4月
固定資産税、不動産取得税、登録免許税などの計算の基礎になる。
家の売買をするときには、不動産取得税と登録免許税(不動産を登記するときに課せられる税金)の計算に関わってきます。
家の売買に関わる税金を知りたい方はこちらの記事を参照してください。
課税標準額は、税率をかけて固定資産税額を算出する基になる金額です。通常、課税標準額と評価額は同一額となります。
しかし、課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低くなります。
特例措置は政府が景気の刺激策として、期間限定でしばしば用いられます。
土地の評価額は、現況の地目に応じて評価された金額です。
公示価格
- 決定する機関 国、国土交通省
- ーーー
- 基準日 1月1日、毎年変更される
- 公表日 3月下旬
公示とは公(おおやけ)の機関が一般の人に示すことです。ここでの公の機関は国土交通省です。
公示価格は国が土地の価格を決めています。
この価格は、不動産取引価格や税金の計算の根拠となります。
公示された土地の価格が公示地価です。
公示価格を調べたいときは国土交通省のホームページで調べることができます。
基準地標準価格
- 決定する機関 都道府県
- 公示価格を100%とすると、その100%の価格になる
- 基準日 7月1日
- 公表日 9月下旬
公示価格の補足となる価格です。
公示価格の半年遅れの基準日と公表日になっています。
公示価格を見て準備する価格なので・・・、そういうことですね。
相続税評価額
- 決定する機関 国、国税庁
- 公示価格を100%とすると、その80%の価格になる
- 基準日 1月1日、毎年変更される
- 公表日 7月1日
相続税、贈与税の計算の基礎になります。
路線価と言い換えられることがあります。
相続税評価額を調べたいときは国税庁のホームページを調べます。
路線価
相続税評価額と同じ
公示地価
公示価格と同じ
公示価格によって決められた土地の価格です。
課税標準
税金の額を計算するときに用いられる値
例)固定資産税評価額、抵当権設定登記の場合は債券金額、
課税標準は特例などの措置により計算対象の時期によって変わってきますので、注意してください。
ちなみに、特例の場合は原則で計算した税金よりも安くなる場合が多いです。
<豆知識>不動産の登記には所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記などがあります。
まとめ

税金の計算するときはいろんな〇〇価格、✖️✖️価、○✖️△価額が出てきて訳分からなくなってしまった人も、この記事を読むことで頭の整理ができたら嬉しいです。
税金を制するものは蓄財を制するとも言われますから、税金に関わる勉強をこれからも続けたいと思います。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます。
それでは、また。